アイデアが生まれる瞬間とは? 漫画家と化学者の共通点
2024年05月23日

「化学×〇〇」という形式で、レゾナックの経営陣と異業界の第一人者が語り合う「Resonac Dialogue(レゾナック ダイアログ)」。
第2回目は、「化学×漫画」をテーマに、アニメがきっかけで科学を目指したCTO福島と、『Dr.STONE』や『トリリオンゲーム』などヒット漫画の原作を手掛ける稲垣理一郎氏が対談。
「時代を捉え、変化を恐れない」ことが大事だと考える二人は、新しい発想をどう生み出すのか?
漫画『Dr.STONE』が科学の入り口に
福島:『Dr.STONE』は難しい科学技術の原理原則をしっかり描いてるのに、この面白さをわかりやすく表現していてすごいですね。どのキャラクターも本当に魅力的で。主人公の「千空」の父親が出てきたところでグイッと引き込まれました。
稲垣:技術の専門家にそう言っていただけると、うれしいですね(笑)。
福島:私が小さい頃に読んでいたら、今よりもっと好奇心旺盛な、よりアクティブな研究者になっていたんじゃないかな。この作品をきっかけに、科学者を志した子どもたちが大勢いるだろうなと思いました。
稲垣:ついこの間も、「千空をまねて水晶板を削り出して、真空管をつくった」とSNSで投稿してくれた方がいたんです。その熱意にビックリしましたね。
福島:さまざまな科学技術が登場するストーリーは、どうやって考えているんですか?

株式会社レゾナック・ホールディングス 執行役員 CTO(最高技術責任者) 福島 正人
稲垣:『Dr.STONE』は他の漫画とは異なる、ちょっと特殊なつくり方をしていました。
福島:それはどんな?
稲垣:科学の話なので、技術的に可能か・不可能かがベースにあるんです。なので、大まかな話の流れが出来たら、科学監修の先生に聞いて、可能であれば具体的なプロセスを考えてもらいます。同時に私はストーリーを固めていきました。
福島:アイデアが技術上の制約を受けるんですね。「技術的に無理」と言われたことは?
稲垣:あります。よく覚えているのが、ディスプレイを作る回。本当は、コンピューターゲームを作って見せたかったんです。大抵は何らかの方法を考案してくれますが、そのときだけは「この段階の科学技術では、半導体製造に必要なシリコンの純度を実現できません。メモリがないのも致命的なので無理です」と。
福島:あぁ、レゾナックの技術があれば実現できるのに(笑)。高純度シリコンを精製するための、「高温・高密度・真空」の状態を作るのはなかなか難しいですね。
稲垣:やはりそうなんですね! 半導体はあらゆるところに使われているのでハードです。

漫画原作者 稲垣 理一郎氏
「興味」がイノベーションの源泉に
稲垣:福島さんは、どうして技術者になったのですか?
福島:小学生のときにアニメ『宇宙戦艦ヤマト』に魅了されて。「自分でつくったロケットで宇宙に行きたい!」と思ったのがきっかけですね。その後、勉強していくうちに「自分は宇宙のことを知りたいんだ」と気が付いたんです。宇宙って、謎が解明されたと思ったら、また新しい謎が生まれるじゃないですか。「謎を解明すること」に興味が移り、その手段である科学を選択したんです。
稲垣:まさに千空じゃないですか(笑)。
福島:マインド的には同じかもしれませんね。(レゾナックの前身の)昭和電工に入社してからは、ハードディスクの研究・開発に長いこと携わってきました。

稲垣:そもそもなんですが、ハードディスクとかコンピューターのようなテクノロジーをよく思いつくな、と。そこまで思い浮かべることができるのがすごい。
福島:数学の世界の“二進法”と物理の世界の“磁力”をくっつけた人がいるんです。発想力が豊かですよね。
稲垣:研究するときには最終形を考えないこともありますよね。「わかんないけど、とりあえず面白いものの理屈を見つけておこう、これをどう使うかはまた後で」みたいな(笑)。
福島:そうなんです。技術者や研究者は興味を持つことが大事。「面白いな、いつもと違うな」と思ったら突き詰める。「何かの役に立つかな?」という視点も必要です。
先生はどういったことからアイデアを見つけているんですか?
稲垣:私は普段の生活のなかで、新しい感覚を覚えたときや、プラス・マイナスの感情が動かされたときがポイントです。「これを形にしたい」という思いが湧くんですよ。たとえば、漫画『スラムダンク』の主人公・桜木花道が、勝てない相手に対して、相手選手のユニフォームを引っ張ってボールを奪って得点するシーン。「ずるいっ!」と。
福島:「少年漫画の主人公が、こんなことしていいのか⁉」と。
稲垣:そうです。その感覚が新鮮で面白くて。“笑い”でもあるし、ある種の“破壊”でもある。このときの感覚を抽出して、磨いて形にしたのが『アイシールド21』の蛭魔妖一というキャラクターです。

福島:まさにイノベーターですね!起業家が「この技術を使って何か面白いことをやってやろう」という発想とすごく似ている。
稲垣:『Dr.STONE』も、「ゼロから科学をつくれるのか?」という興味に「何かを地道にやり遂げるのはかっこいい」という個人的な思いを掛け合わせ、「文明がリセットされた地球を、超地道に科学で完全復興させていく」というストーリーが生まれました。
福島:興味や気づきの面白さを作品に昇華させているんですね。
「市場の声」に耳を傾けて、変化し続ける
福島:連載している時は「読者の声」を気にされますか?
稲垣:割と (笑)。連載していた雑誌は、人気がないと新連載でも3週間程度で打ち切りが決まってしまうシビアな世界なので、生き残るための戦略を考えます。『Dr.STONE』はスタートの手ごたえが良かったので、「ちょっと科学の要素も取り入れてみよう」と挑戦してみたら、人気がポンって上がって、「あ、これいけるな!」と。
福島:読者とのオープンイノベーションですね。研究開発においても、ユーザーの意見に耳を傾けることがとても大切なんです。開発途中のものの評価を聞くことは、結構、勇気がいるんですけど、「お客さまの意見を聞いてみよう!」と促しています。でも、なかなか難しいんですよ。
稲垣:なぜですか?
福島:研究者の多くは実験に時間を費やし、ヒアリングのスキルをあげる機会はほとんどありません。しかし、研究をしているからこそ、相手の意見や悩みを聞いたらひらめくような「ポイント」がある。先生が「読者は面白いって言ってくれるかな」というのと一緒です。研究者には、どんなにもがいてもいいから、自ら探ることをしてほしいと思っています。

稲垣:「市場の声」って本当に大事ですね。『Dr.STONE』の連載を開始したときは、ありがたいことに人気が出たのですが、その直後に少しだけ下がった。絶対に人気が取れると思っていた回でもとれなかった。これが一番やばい。
福島:時代と感覚がずれている、と。そこから、どのように変えていったのですか?
稲垣:編集者と他の漫画の人気推移などデータを分析して、いろんな仮説を立てました。それでも人気が取れなかったら、自分の感覚がずれたままということ。結果、すぐに人気が戻りましたが、昔のやり方のままではだめですね。倫理観を含めて、読者の感覚が研ぎ澄まされ、変化していることに気がつきました。
福島:私も「変わらなければ衰退する」と常々言っています。むしろ、変わることでようやく現状維持ができるとも思っています。
稲垣:「変化を恐れない」というのは大事ですね。安定期に入ってきたという感覚にあぐらをかいてしまうと、70点の作品しかつくれなくなってしまう。そうならないために、仮説検証をしながら、リスクがあることにもチャレンジするよう意識しています。
福島:変化していくために、部門や企業の垣根を越えてノウハウを共有したり、失敗できる場をつくっていく。レゾナックではそういった共創型の研究開発を進めていく計画です。自分も変わることを楽しめる人間でありたいですね。

最先端技術で"ワクワク"を生み出していく
稲垣:近い将来、AIは間違いなく人間の脳に追いつくと思っているんですが、どうでしょう?
福島:私も同じ考えです。AIがイノベーションを起こしてくれるようになるかもしれない。
稲垣:今はAIを補助的に使っていますが、もっと進化して、AIが面白い作品を描いてくれるんだったら大歓迎です。私の考えた最高に面白い作品が自動的にできるんだったら、自分では描かないかもしれませんね(笑)。
福島:化学業界でも、AIの力によって研究開発のスピードが年々上がってきています。予測計算も早くなって仮説検証にかかる時間も短縮されるから、新しいアイデアを次々試すことができる。
稲垣:文化や技術の究極的な最終ゴールは、ドーパミンを放出させて快感や満足感を得ることだと思っています。そう考えるとAIはドーパミンがなく、自分の快楽のために動かない。「AIが普及すると何もやらなくなる」という人がいるが、そうではなくAIをどんどん利用し始めるんじゃないかな。
福島: 研究の分野でも「見つけた!」という瞬間は信じられないくらいの高揚感があります。AIでモノづくりが変わろうとしているので、ワクワクしています。
稲垣:「こういうのがやりたい」と思ったときに、結果が早く出るってことですね。より研究が楽しくなる。
福島:そうそう。ホットな気持ちの間に結果がでると「面白い!」と次に進めます。レゾナックも計算科学の活用によって成果を出しつつあるんですよ。今後さらにアイデアが生まれやすくなるんじゃないかな、と思います。

化学も、漫画も、多くの人が夢をみる場所でありたい
稲垣:スポーツや漫画で「楽しい」という感覚は一般的なものですけど、科学的な快感はメジャーではない。そういったことで理系の人が減ってしまうと社会の損失だと思うんです。『Dr.STONE』では「科学的思考の快感」って面白いんだよ、と伝えたかった。これを読んだ人が理系に行くかはわからないけど、その楽しみを知っているか否かでは違いますからね。
福島:確かに選択肢が増えますよね。
稲垣:最近は、漫画家も目指す人が減ってきているように感じます。人が職業を志す理由は、「面白い」「楽」「儲かる」「モテる」などさまざま。「漫画家は稼げる、夢のある仕事だ」ということをアピールすると、目指す人が増えるのではないかと思います。
福島:化学業界にも通ずるところがあります。画期的な発明をした研究者には、対外的にもわかりやすい形で評価しないといけないな、と。
稲垣:たとえば、「賞金1000万円」とかですかね?
福島:そのぐらいまで振り切った方がわかりやすいかな(笑)。選択肢が無数に広がっているこの時代に、価値あるものを世の中に提供していく人材を集めるには「レゾナックに入ると楽しい、やりがいがある」と思ってもらえるかが勝負です。なので、研究者の評価、待遇面も考えていく必要があると思っていますね。
稲垣:CTOとしての「野望」みたいなものはあるんですか?
福島:全社員に「レゾナックは情熱をかける会社だ。働いていてすごく楽しい」と思ってもらうことが目標ですね。100年続く技術をつくって、世の中の発展に寄与する会社にしたい。そのためには、やはり「共創」がカギになると思います。
部署、部門はもちろん、企業間も横断して、互いにリスペクトし合いながら、みんなでイノベーションを起こしていく。世界中の研究者をつなぐプラットフォームのような存在にレゾナックを発展させていきたいと思います。
稲垣:いいですね。「面白い」って、人が何かを始めるときの一番の原動力だと思います。そして、「面白い」が増えると、みんなが幸せになるというのが、私の思想の根幹です。今後、どんなテーマで作品をつくるかわかりませんが、「面白い」をしっかり伝えていきたいですね。ぜひレゾナックさんももっともっと、面白い会社にしてください。
福島:ありがとうございます。頑張ります。今日は本当に楽しかったです。
稲垣:こちらこそ、ありがとうございました。また今度、技術の話を聞かせてください。

稲垣 理一郎
漫画原作者。
週刊少年ジャンプにて、村田雄介を作画に迎え2002年から2009年まで『アイシールド21』を連載。その後、2017年からはBoichi作画による『Dr.STONE』を同誌で連載し、第64回小学館漫画賞の少年向け部門を受賞。2020年11月からは、ビッグコミックスペリオール(小学館)にて、池上遼一とタッグを組んだ『トリリオンゲーム』を連載中。同作にて第69回小学館漫画賞受賞。
福島 正人
株式会社レゾナック・ホールディングス 執行役員 CTO(最高技術責任者)。
1991年早稲田理工卒、昭和電工(現・レゾナック・ホールディングス)入社、エレクトロニクス事業本部HD工場配属。2014年昭和電工エレクトロニクス(以下、SEL 現・レゾナック・エレクトロニクス)研究開発センター リーダー、2015年ハードディスク事業部 営業部長、2019年デバイスソリューション事業部 営業部長 兼 生産技術統括副部長、2020年デバイスソリューション事業部 技術開発統括部長 兼 SEL研究開発センター長を経て、2023年1月から現職に就任。
関連記事
-
NEW
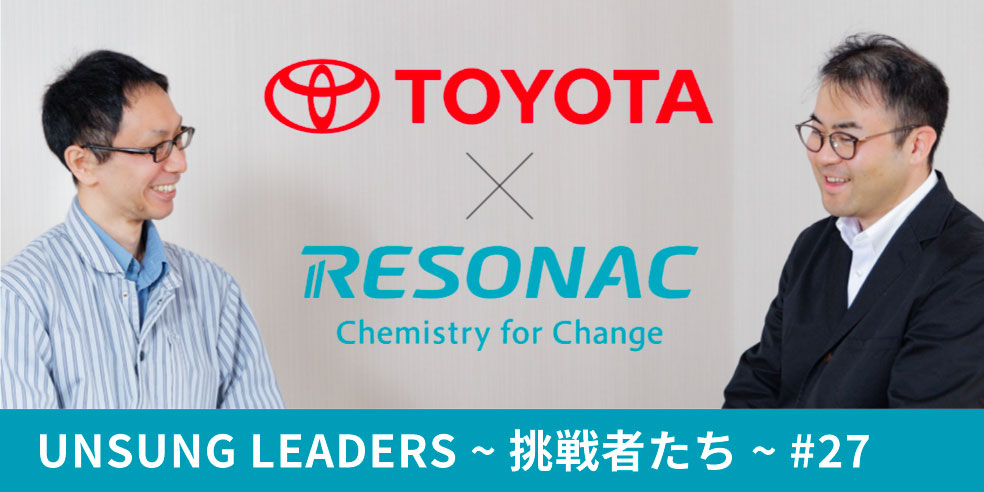 2024年07月08日NEW
【トヨタ自動車×レゾナック】
2024年07月08日NEW
【トヨタ自動車×レゾナック】
アルミ材料の共創が導くカーボンニュートラル サステナビリティ 共創 対談 アンサングリーダー カーボンニュートラル 自動車 -
NEW
 2024年07月08日NEW
一番は「自分で考える」こと。慶應高野球部・森林監督と語る人材の育て方
対談
人材育成
2024年07月08日NEW
一番は「自分で考える」こと。慶應高野球部・森林監督と語る人材の育て方
対談
人材育成
-
NEW
 2024年06月27日NEW
“熱意”は相手に伝わる。世界的指揮者・西本氏と語る個性を活かす組織の作り方
共創
対談
チームビルディング
2024年06月27日NEW
“熱意”は相手に伝わる。世界的指揮者・西本氏と語る個性を活かす組織の作り方
共創
対談
チームビルディング
-
 2024年02月09日
AI半導体時代到来。次の技術革新のカギはどこだ?
次世代半導体
対談
メディア掲載
パッケージング・ソリューションセンタ
2024年02月09日
AI半導体時代到来。次の技術革新のカギはどこだ?
次世代半導体
対談
メディア掲載
パッケージング・ソリューションセンタ
-
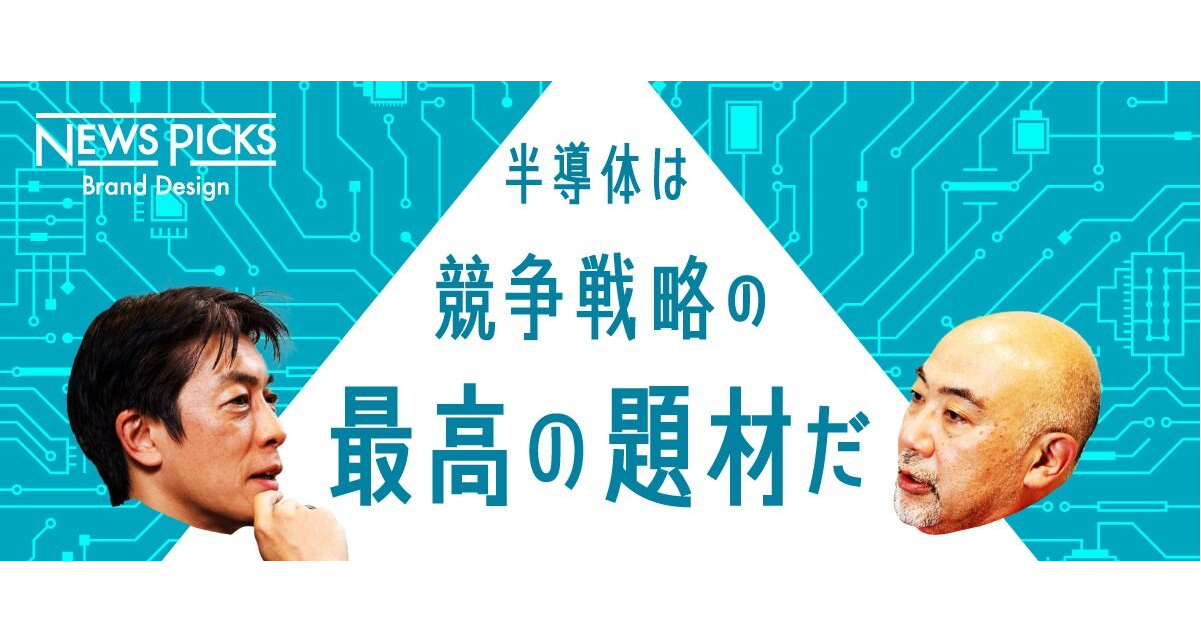 2024年01月29日
“面倒くさい”こそ参入障壁。日本半導体の勝ち筋はどこだ?
次世代半導体
チーム経営
対談
メディア掲載
2024年01月29日
“面倒くさい”こそ参入障壁。日本半導体の勝ち筋はどこだ?
次世代半導体
チーム経営
対談
メディア掲載
-
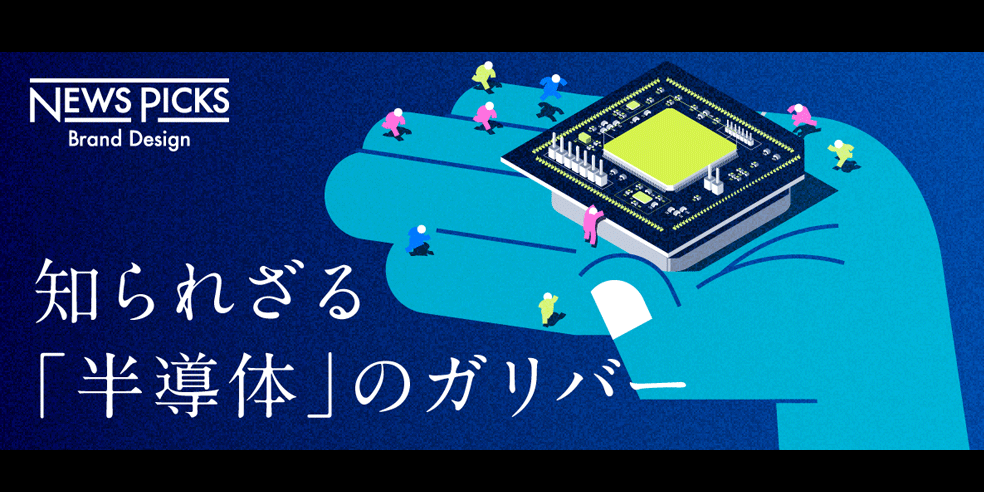 2023年11月22日
半導体進化の“カギ”を握る「レゾナック」の戦略
2023-11-02 NewsPicks Brand Design
次世代半導体
チーム経営
人的資本経営
対談
チーム髙橋
スピード変革
メディア掲載
2023年11月22日
半導体進化の“カギ”を握る「レゾナック」の戦略
2023-11-02 NewsPicks Brand Design
次世代半導体
チーム経営
人的資本経営
対談
チーム髙橋
スピード変革
メディア掲載
-
 2023年11月22日
新生レゾナックCEOが目指す「スピード大変革」の内幕 - 最優先で「人材育成」に取り組む理由とは?
本記事はNewspicksの動画を転載したものです
チーム経営
人的資本経営
対談
チーム髙橋
動画
スピード変革
メディア掲載
2023年11月22日
新生レゾナックCEOが目指す「スピード大変革」の内幕 - 最優先で「人材育成」に取り組む理由とは?
本記事はNewspicksの動画を転載したものです
チーム経営
人的資本経営
対談
チーム髙橋
動画
スピード変革
メディア掲載
-
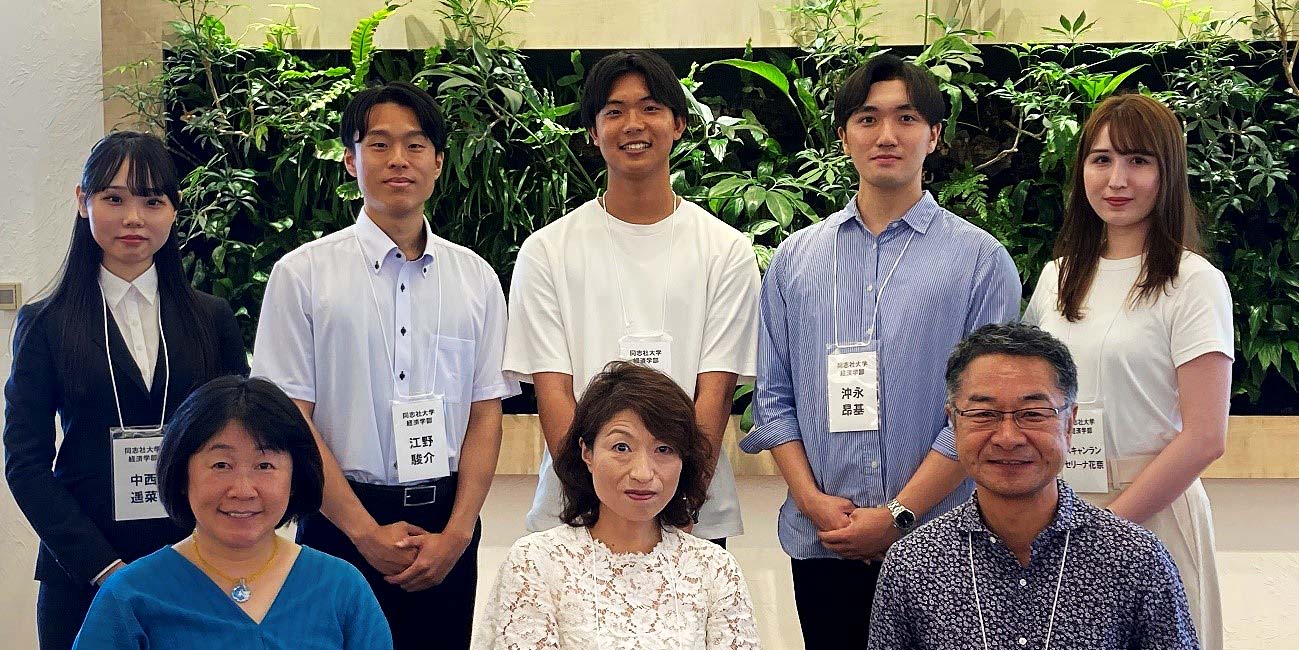 2023年10月10日
素材産業への意見と期待~CFOと同志社大 新関ゼミとの座談会~
サステナビリティ
人的資本経営
対談
2023年10月10日
素材産業への意見と期待~CFOと同志社大 新関ゼミとの座談会~
サステナビリティ
人的資本経営
対談
-
 2023年08月22日
大学生と語る「素材産業が社会課題解決のカギとなる理由とは?」
サステナビリティ
対談
2023年08月22日
大学生と語る「素材産業が社会課題解決のカギとなる理由とは?」
サステナビリティ
対談
